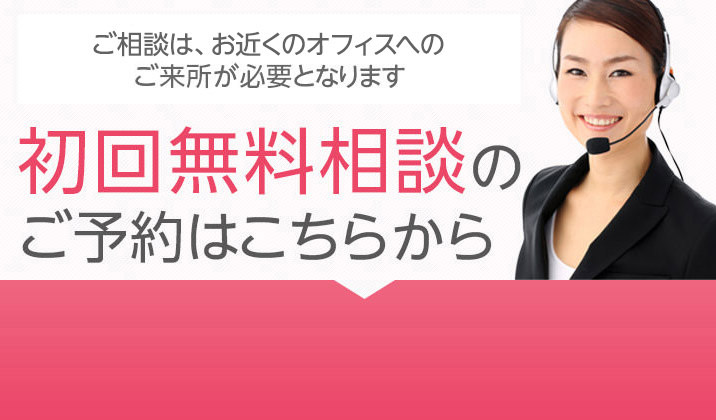離婚に伴う子どもの扶養控除関連と健康保険手続き、養育費の扱いはどうなる?
- 離婚
- 離婚
- 扶養
- 控除

夫婦が離婚をしたときに気になるのが、離婚後の扶養についての問題です。
豊中市では、離婚後子どもを引き取り扶養する方に向け、養育費の受け取りをサポートする施策を行っていますが、子どもを扶養家族としたほうが扶養控除などの問題が起きづらいのか、健康保険はどうすべきか悩まれる方もいるでしょう。
本コラムでは、離婚した場合における子持ち女性が知っておきたい、扶養控除や健康保険の概要から、養育費の扱いについてベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚後は税金の額が変わる? 扶養控除の基礎知識
「扶養」という言葉にはさまざまな意味があります。まずは、税法上の「扶養」に関して、扶養控除について以下で説明します。
-
(1)扶養控除によって税金が減税される
扶養控除とは、子どもや親等扶養控除の対象となる親族がいる場合に、納税者の所得から一定額の所得控除を受けられる、所得税法における制度のことをいいます。
納税義務者に家族がいて面倒をみているときには、独身者と比べて生活費の負担が多くなります。そこで、税法上、このような納税者の事情に配慮して、扶養者の人数に応じて税金の負担を軽減しようとしたものが扶養控除の制度です。扶養控除の適用を受けることによって、支払うべき税金が減額されることになります。 -
(2)扶養控除の要件とは
扶養控除を受けるためには、扶養の対象となる親族が以下の要件を満たす必要があります。離婚にあたって扶養控除を受ける場合には、一緒に生活する子どもが以下の要件を満たすかどうかがポイントとなります。
① 納税者の扶養親族で生計を一にする人
親族とは、配偶者を除く6親等内の血族と3親等内の姻族です。子どもについては、実子であるか養子であるかを問わず親族の範囲に含まれます。
生計を一にするとは、納税者が扶養親族を養っていることをいい、必ずしも同居をしている必要はありません。たとえば、一人暮らしをしている大学生の子どもに仕送りをしている場合でも生計が同一であると判断されます。また、離婚後に毎月継続的に養育費を支払っている場合にも、生計が同一であると判断されます。
したがって、子どもと一緒に生活をしていない非親権者も扶養控除を受けられることがあります。
② 年間の合計所得金額が48万円以下の人
扶養控除の対象になる親族の年間合計所得金額が48万円以下であることが必要になります。以前は38万円以下とされていましたが、令和2年から48万円以下に引き上げられました。
③ 事業専従者でない人
事業専従者とは、個人事業主である納税義務者の事業を手伝っている家族のことをいいます。納税義務者が個人事業を営み、扶養親族に対して給料を支払っているときには、扶養控除を受けることはできません。
④ 他の人の扶養親族や控除対象配偶者になっていない人
扶養控除は、二重に受けることはできませんので、他の人の控除対象扶養親族などになっていないことが要件となります。離婚後の元夫婦がともに扶養控除の要件を満たすときには、どちらか一方しか扶養控除は受けられませんので、どちらが扶養控除を利用するかどうかは離婚時に話し合って決めておきましょう。
⑤ その年の12月31日時点で16歳以上であること
扶養控除対象者は、その年の12月31日時点で16歳以上であることが必要になります。16歳未満の子どもに対しては、児童手当が支給されますので、扶養控除は受けられません。 -
(3)扶養控除の控除額
子どもを扶養控除対象者として扶養控除を受ける場合には、その年齢に応じて以下の金額が所得から控除されることになります。
- ① 一般扶養親族(16歳以上18歳以下):38万円
- ② 特定扶養親族(19歳以上22歳以下):63万円
- ③ 成年扶養親族(23歳以上69歳以下):38万円
2、離婚後の健康保険|必要手続きを加入保険別に解説
離婚後の「扶養」については、税法上だけでなく社会保険上も検討が必要になります。社会保険上の扶養に関しては、以下のように健康保険の手続きが必要になります。
-
(1)健康保険から国民健康保険への変更
婚姻中は夫の扶養家族として夫の会社の健康保険に加入していたときには、離婚によってその資格を喪失することになります。新たに国民健康保険に加入する場合には、夫の勤務先の会社から「資格喪失証明書」を発行してもらい、市区町村役場の窓口にそれを持参し、国民健康保険の加入手続きを行います。
-
(2)健康保険から別の健康保険への変更
妻が仕事をしている場合には、夫の扶養家族から外れた後に、妻の勤務先の健康保険に加入するという方法も可能です。自分の会社の健康保険に加入するときには、その旨勤務先に申請をするだけで手続きができます。
-
(3)国民健康保険から新たな国民健康保険への変更
夫が個人事業主などの場合には、夫婦ともに健康保険ではなく国民健康保険に加入しているはずです。婚姻中は、夫を世帯主とした国民健康保険に加入していますので、離婚後も引き続き国民健康保険に加入するという場合であっても、世帯主の変更手続きが必要になります。そのため、離婚後は、市区町村役場の窓口で世帯主変更届を提出するようにしましょう。
-
(4)国民健康保険から健康保険への変更
夫が世帯主として加入していた国民健康保険から自分の勤務先の健康保険に変更をするときには、その旨勤務先に申請をするだけで手続きができます。
お問い合わせください。
3、子どもの扶養|健康保険や養育費はだれが負担する?
離婚によって子どもの扶養はどうなるのでしょうか。以下では、子どもの健康保険と養育費について説明します。
-
(1)子どもの健康保険
多くの夫婦では、婚姻中は夫の扶養親族として、妻と子どもが夫の会社の健康保険を利用しています。離婚後は、妻が子どもを引き取り、上記のとおり、健康保険の変更手続きを行いますが、それによって子どもの扶養も変更になるというわけではありません。
何も手続きをしなければ、引き続き夫の扶養家族として夫の会社の健康保険に加入した状態となります。妻が子どもも自身の健康保険や国民健康保険に加入させたいと考えたときには、自身と同様に子どもについても別途手続きをする必要があります。 -
(2)子どもの養育費
離婚した夫婦に子どもがいるときには、子どもを監護養育している方は、非監護親に対して養育費を請求することができます。これは、親が子どもに対して負う扶養義務の一環として支払われるものです。
子どもの養育については、離婚時の夫婦の話し合いによって決めることになります。養育費の金額については、法律上特に決まりはありませんので、当事者が合意をした金額が養育費の金額となります。
もっとも、養育費の算定にあたっては、裁判所が公表している養育費算定表を利用することによって、ある程度の相場を知ることが可能です。養育費算定表では、夫婦双方の収入と子どもの年齢によって構成された表によって簡単に養育費の金額の相場を知ることができます。
養育費の金額がなかなか決まらないというときには、養育費の算定表を利用するのも有効な方法です。
なお、ベリーベスト法律事務所では、養育費算定表を参考にした 養育費計算ツール をご用意しておりますので、お気軽にお使いください。
4、子どもの親権や扶養のルールは離婚前に話し合おう
扶養に関する取り決めについては、離婚後の生活を送るうえで必要不可欠となります。弁護士に相談をしながら適切な内容となるように進めていきましょう。
-
(1)子どものためにも適切な養育費を取り決める
離婚をして子どもの親権を獲得した親としては、どの程度の養育費をもらうことができるかということが重大な関心事です。
離婚にあたって、養育費の取り決めをしていなかったり、口約束だけで終わらせてしまった夫婦では、離婚後に養育費の支払いがなかったり、途中で滞ってしまうということもあります。養育費は、子どもが健全に発育していくために不可欠なお金ですので、扶養権利者としては、扶養義務者に対してきちんと請求するべきです。
離婚するときに親権や養育費を決める際には、養育費の金額や支払期間などをめぐって争いになることが多く、話し合いで解決しないときには、家庭裁判所の調停や審判という手続きにまで発展することがあります。このような事態を避けるためには、多少労力はかかりますが、離婚時にきちんとした内容で取り決めをしておくことが大切です。これによって、将来の養育費の支払いを確実なものとすることができます。
そのためには、弁護士のサポートを受けながら進めていくことが有効ですので、離婚をする前に必ず弁護士に相談をするようにしましょう。 -
(2)養育費以外の扶養の取り決めについてアドバイスをもらえる
離婚にあたっては、養育費以外にも扶養に関しては、扶養控除をどちらが受けるか、健康保険の扶養を外してもらうことができるかどうかについて夫婦で話し合いを行わなければなりません。
扶養控除については、要件を満たす限り、離婚後の元夫婦のどちらでも利用することができます。扶養控除については、収入が高い方が利用したほうが納める税金を少なくする効果が大きくなります。そのため、扶養控除については夫が利用することとして、それによって所得が増えた分については、養育費として還元してもらうといった交渉をすることも可能になります。
他にもさまざまな方法がありますが、弁護士に相談をすることによって、夫婦の具体的な状況に応じて、適切な法的アドバイスをもらうことが可能です。
お問い合わせください。
5、まとめ
子どもがおられる夫婦が離婚した場合、「扶養」に関する手続きが多岐にわたります。そのため、離婚をする前から正確に理解しておくことが重要です。特に養育費の取り決めは子どもの生活に直結するため、慎重かつ適切な対応が必要です。子どもの将来を真剣にお考えになるのであれば、適切な書面に二人で決めた条件を記した離婚協議書を作成し、強制執行文言をつけた公正証書にしておくなど、法的に有効な契約を取り交わすことをおすすめします。
また、離婚する際は、親権や養育費だけでなく、財産分与などお金について取り決めるべきことが多数あり、いずれも新たな生活に影響を及ぼします。離婚後の扶養や養育費などについてお悩みの方は、離婚問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士がアドバイスを行います。お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています