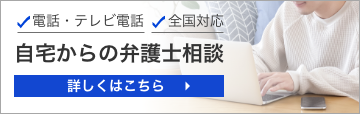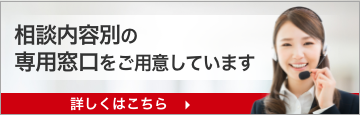労災からの復職時に配置転換は可能? OK・NG判断ポイント
- 労働問題
- 労災
- 復職
- 配置転換

「令和4年度統計年報」(大阪労働局)によると、令和4年度に大阪府内で発生した休業4日以上を要する労働災害は2万2742件でした。
労災(労働災害)に遭った従業員が復職する際には、元の部署に復帰するのが原則ですが、従業員の同意や、就業規則に定めた人事権の範囲内であれば、別の部署への配置転換が認められることもあります。
後々の労働トラブルを回避するためには、弁護士のアドバイスを受けながら、配置転換しても問題ないかどうかをよく検討するのが得策です。本記事では、労災から復職する従業員を配置転換が、OKなケース・NGなケースについて、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士が解説します。
1、労災に遭った従業員の復職先はどこの部署?
労災に遭った従業員が職場復帰する際には、元の職場・職務に復帰させるのが原則です。慣れた部署に戻った方が、復職する従業員も働きやすいケースが多いでしょう。
厚生労働省が公表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、新しい環境への適応にはある程度の時間と心理的負担を要し、その負担が疾患の再燃・再発に結び付く可能性があるため、元の職場への復帰を原則とすべき旨が指摘されています。
しかし何らかの事情で、労災から復職する従業員を別の部署へ配置転換したい場合もあるでしょう。たとえば、人員が不足している部署へ移ってもらいたい、労災の原因を作ったほかの従業員と部署を分けたいなどの事情が考えられます。
2、労災からの復職時の配置転換がOKの場合
労災から復職する従業員の同意があれば、休職前とは別の部署へ配置転換することができます。また、従業員の同意がなくても、人事権の範囲内であれば、原則として配置転換が認められます。
-
(1)従業員の同意がある場合
従業員の同意があれば、労災からの復職時に配置転換をすることができます。配置転換をしても、従業員にとって不利益はないと考えられるためです。
ただし、企業側(使用者側)が従業員に対して無理やり同意を迫るなど、従業員の同意が任意ではないと思われる事情がある場合は、同意がないものとして配置転換が違法となるおそれがあるのでご注意ください。 -
(2)配置転換が人事権の範囲内である場合
労働契約において、企業側は従業員に対する人事権を有します。人事権の範囲内で企業から受けた指示には、従業員は原則として従わなければなりません。
配置転換も、企業が有する人事権の行使として、従業員の同意がなくても行うことができる場合があります。
従業員の同意なく配置転換を行うためには、労働契約または就業規則において、配置転換の根拠規定が定められていることが必要です。具体的には、「業務上必要がある場合は、勤務場所や業務の変更を命ずることがある」といった定めが置かれている必要があります。配置転換の根拠規定が定められていれば、原則としてその範囲内において、従業員の同意がなくても配置転換を行うことができます。
3、労災からの復職時の配置転換がNGの場合
-
(1)契約上、配置転換が認められていない場合
前述のとおり、従業員の同意なく配置転換を行うためには、労働契約または就業規則における根拠規定が必要です。
したがって、労働契約または就業規則において配置転換を行うことがある旨の根拠規定が定められていなければ、配置転換は認められません。
たとえ配置転換を行うことがある旨を定めていても、個々の従業員によって、職種を限定する特別な合意がある場合は、会社に認められる配転命令権はその合意の範囲内に限定されます。具体的には、労働契約の内容として、勤務場所・職種が限定されているケースがあります。なお、このような職種を限定する合意は、医師などの専門性の高い資格や技能が必要な職種については、明示がなくても、職種を限定する合意があると認められる可能性があります。
また、「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(令和6年4月1日施行)。そのため、今後は労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミングで雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所と従事すべき業務の「変更の範囲」の明示が求められ、その限りで配転命令権も制限される可能性があります。 -
(2)配置転換が不必要・不合理である場合
労働契約または就業規則の規定上は配置転換が可能な場合であっても、目的が不正である配置転換は、人事権の濫用として無効となります。
配置転換が人事権の濫用に当たり、無効と判断される可能性が高いのは、以下のようなケースです。- 配置転換を行う業務上の必要性がない場合
- 配置転換が不当な動機や目的に基づく場合
- 配置転換によって、労働者が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負う場合
業務上の必要性は、会社の合理的な運営のためといえる程度の理由があれば、比較的広く業務上の必要性が認められています。また、不当な動機や目的とは、従業員への嫌がらせ目的や従業員を退職へ追い込むために配置転換がなされたような場合を指します。
特に転勤を伴う配置転換については、従業員の状況を考慮して適否を判断する必要があります。
過去には、高齢の家族や障害のある家族を介護する従業員に対して、遠方への転居を伴う配置転換を命じたことが、人事権の濫用として無効と判断された裁判例があります(大阪高裁平成18年4月14日判決)。
労災から復職したばかりの従業員の配置転換を検討する際には、労働契約や就業規則のルールを画一的に適用するだけでなく、従業員の状況にも配慮して適否を判断しましょう。
4、会社が従業員と揉めた場合の解決策
会社が従業員と揉めてしまった場合は、協議または労働審判・訴訟などの法的手続きによって解決を図りましょう。
-
(1)従業員との協議
企業と従業員の間のトラブルは、基本的には協議によって解決することが望ましいです。協議がまとまれば早期にトラブルを解決でき、企業と従業員の間に大きなしこりが残ることも避けられます。
従業員との協議をまとめるためには、従業員側に対してメリットを提示することがポイントです。配置転換に関する協議であれば、賃金の引き上げや福利厚生の改善などを提案すれば、従業員側が受け入れる可能性が高まります。
従業員との協議がまとまったら、合意内容を記載した書面を締結しましょう。合意内容を明確化した上で、さらなる請求をしない旨を約束することで、従業員とのトラブルの再燃を防げます。 -
(2)労働審判
企業と従業員の間のトラブルは、「労働審判」という法的手続きによって解決することも考えられます。
労働審判は、労使紛争を迅速に解決することを目的とした手続きです。裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、調停または労働審判によって労使紛争の解決を図ります。
配置転換については、従業員側がその無効を主張して労働審判を申し立てるケースがあります。労働審判の期日は、原則として3回以内で終結します。そのため企業側としては、最初の期日までに十分な準備を整えることが大切です。
配置転換の有効性が争われる場合は、労働契約・就業規則の根拠規定があることや、配置転換の必要性・相当性が認められることを説得的に主張できるように準備しましょう。
また、労働審判の過程では、労働審判委員会から調停を提案されるケースもあります。企業側として受け入れられる最低ラインを念頭に置きつつ、調停案が合理的であれば、妥協して応じることも検討しましょう。 -
(3)訴訟
企業と従業員のトラブルは、最終的に「訴訟」によって決着が付きます。
労働審判に対して異議が申し立てられた場合は自動的に訴訟へ移行するほか、労働審判を経ずに訴訟を提起することも可能です。配置転換についても、従業員が無効を主張して訴訟を提起するケースがあります。
訴訟の判決は、主に証拠に基づく主張・立証の結果を基に言い渡されます。企業側としては、自社の主張を補強する資料をできる限り豊富に裁判所へ提出することが、勝訴につなげるための重要なポイントです。
配置転換の有効性が訴訟で争われる場合は、労働契約・就業規則に加えて、配置転換の必要性・相当性を説明できる資料を裁判所に提出しましょう。
なお、訴訟の途中で裁判所から和解を提案されることもあります。労働審判における調停と同様に、企業側として受け入れられる範囲内であれば、和解に応じることも検討しましょう。
5、まとめ
労災から復職した従業員は、元の部署に復帰させるのが原則です。ただし、従業員の同意があれば配置転換が認められるほか、労働契約や就業規則における根拠があれば、従業員の同意がなくても配置転換できる場合があります。
ただし、従業員の同意なく配置転換を行う場合、後に従業員とのトラブルが生じるリスクがあります。そのため、事前に弁護士へ相談した上で方針を決めるのが安心です。
ベリーベスト法律事務所は、人事・労務管理に関する企業のご相談を随時受け付けております。従業員の配置転換や解雇に関するトラブル、未払い残業代請求への対応、労災対応など、幅広い問題について弁護士がアドバイスいたします。まずはお気軽に、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています